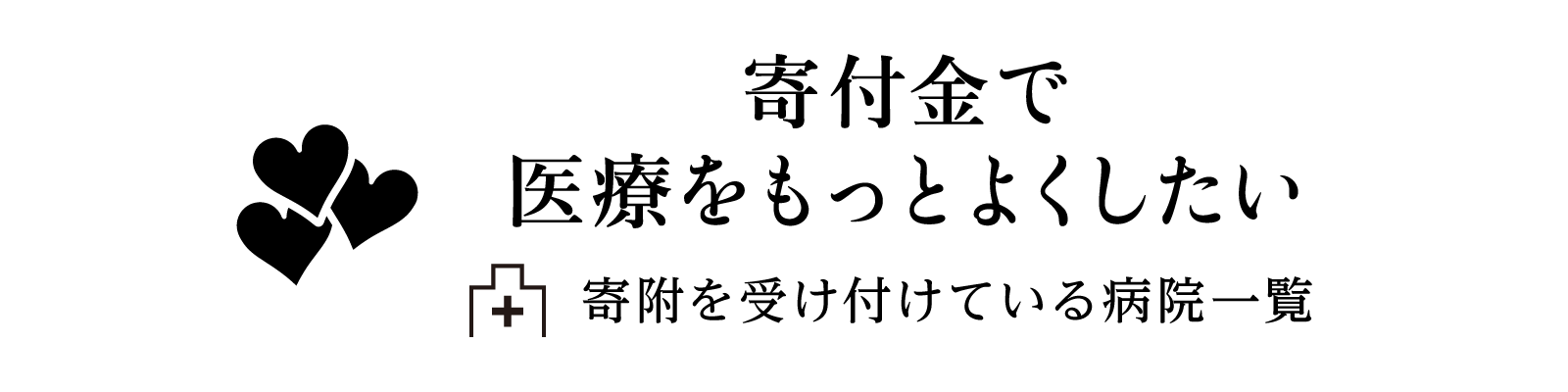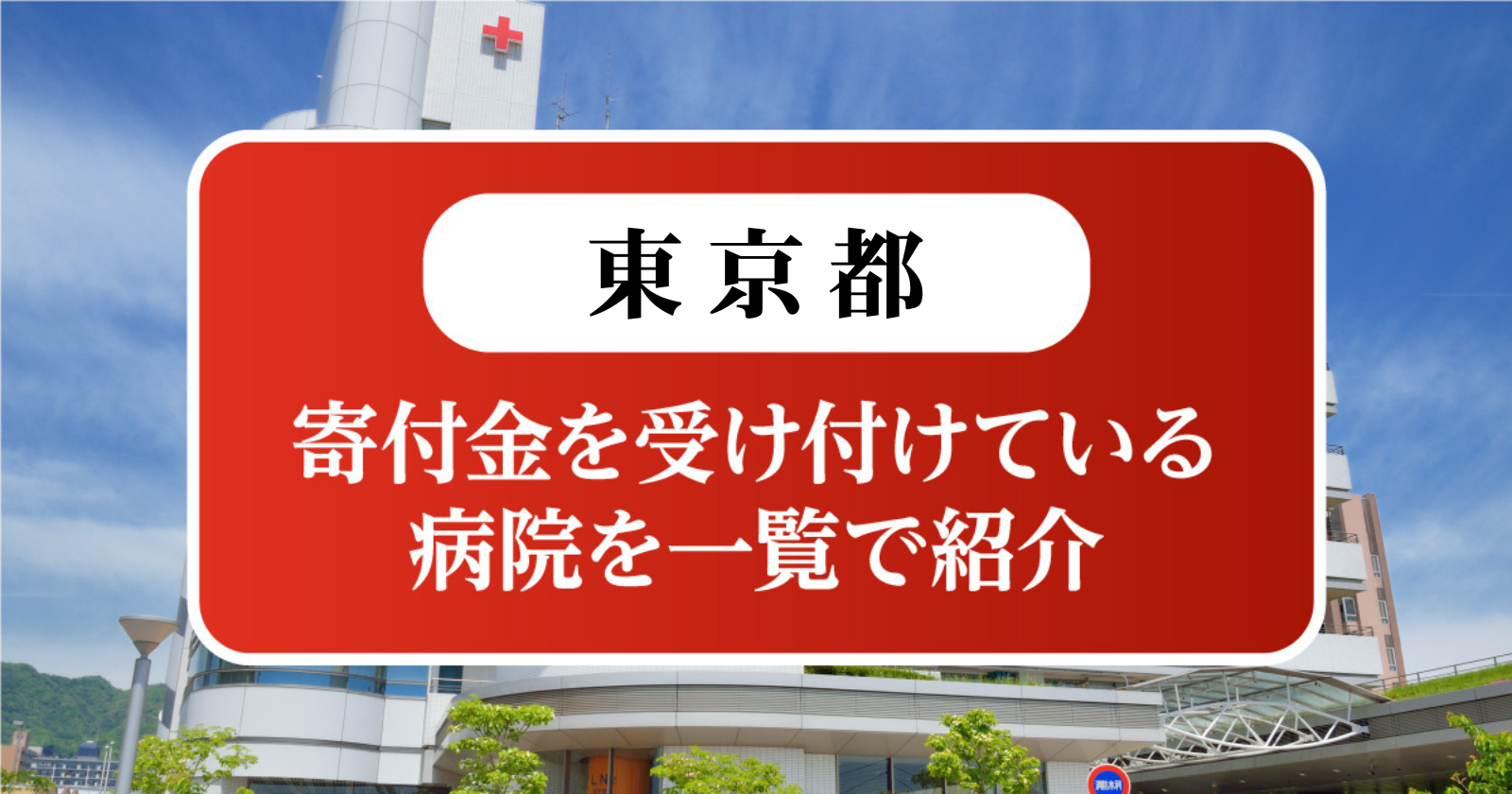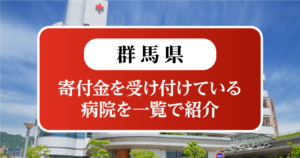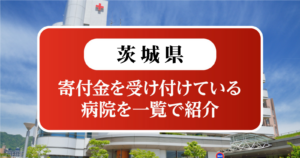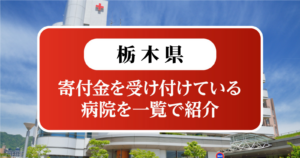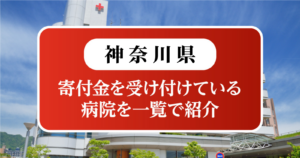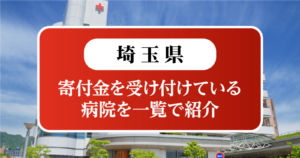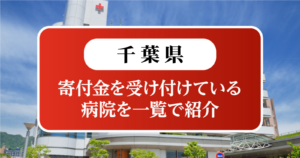板橋区
公益財団法人 愛世会
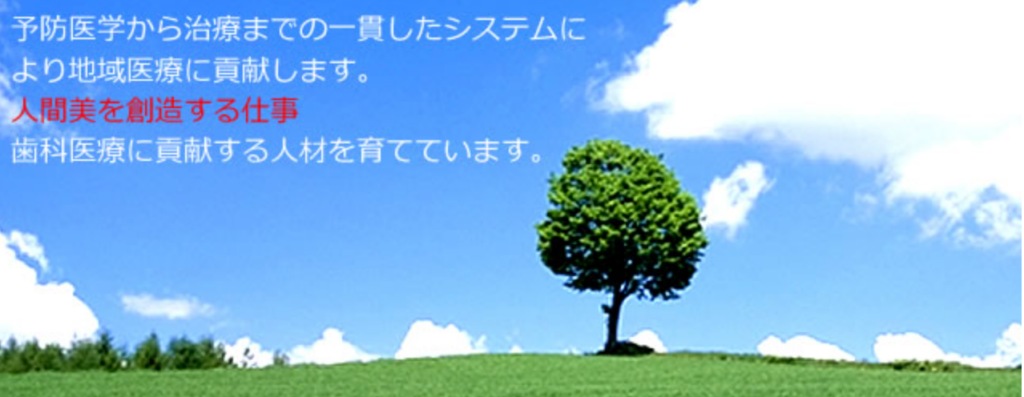
『公益財団法人 愛世会』は、地域医療の充実と福祉の向上を目的に、医療・介護・福祉の分野で幅広い支援を行う法人です。特に、高齢者や障害を持つ方々、生活に困難を抱える方々への医療提供に注力し、誰もが安心して適切な医療を受けられる社会の実現を目指しています。
愛世会が運営する病院では、内科・外科・整形外科などの一般診療に加え、リハビリテーションや緩和ケア、精神科医療にも対応。さらに、救急医療や在宅医療、介護施設の運営を通じて、地域の皆さまの健康と生活を幅広く支える体制を整えています。こうした活動により、高齢者や障害者の方々が住み慣れた地域で安心して暮らせる環境づくりに貢献しています。
愛世会の取り組みは、多くの企業や個人からの寄付によって支えられています。寄付金は、以下のような用途に活用されています。
- 生活困窮者への医療提供
経済的な事情で十分な医療を受けることが難しい方々に対し、適切な診療や支援を提供するための資金として活用されています。 - 障害者支援事業の推進
障害を持つ方々が適切な医療や福祉サービスを受けられるよう、専門的なケアやリハビリテーションの充実を図っています。 - 地域住民の健康増進活動
公衆衛生の向上を目指し、地域全体の健康づくりを支援する取り組みに役立てられています。
愛世会では、寄付金の透明性を重視し、定期的に活動報告を行うことで、支援者の皆さまに資金の活用状況を明確に伝えています。寄付を通じて、地域医療・福祉の発展に貢献し、多くの方々の健康と安心を支えることができます。
寄付の詳細やお申し込み方法については、公式サイトをご覧ください。皆さまの温かいご支援を心よりお待ちしております。
社会福祉法人 日本肢体不自由児協会 心身障害児総合医療療育センター

社会福祉法人 日本肢体不自由児協会は、肢体不自由児・者とその家族を支援し、社会の理解と啓発を促進することを目的に、多岐にわたる活動を展開しています。その中の『心身障害児総合医療療育センター』は、心身に障害をもった子どもたちのための総合的な医療療育相談機関で、社会福祉法人 日本肢体不自由児協会が厚生労働省の委託をうけて運営しています。
「療育とは、現代の科学を総動員して不自由な肢体を出来るだけ克服し、それによって幸にも恢復したら『肢体の復活能力』そのものを(残存能力ではない)出来る丈有効に活用させ、以て自活の途の立つように育成することである」 という故高木憲次先生の療育理念を原点とし、子どもたちが自立した生活を送るための支援を行っています。
このような取り組みを継続し、より多くの支援を届けるためには、皆さまからの寄付が大きな支えとなっています。寄付金は、以下のような事業に活用されています。
- 肢体不自由児療育思想の普及
- 肢体不自由高校奨学生の採用
- 肢体不自由児・者療育キャンプの実施
- 家庭奉仕員派遣事業等、在宅肢体不自由児・者への援助
- 療育相談事業の実施
- 施設、父母の会等への助成
- 療育振興功労者への表彰等
- 訓練器具、生活用具等の購入
- 障害者スポーツの普及推進
- 各種調査、研究
- その他肢体不自由児・者福祉増進のための活動
日本肢体不自由児協会では、寄付金の使途を明確にし、支援者の皆さまに向けて定期的に活動報告を行っています。皆さまからのご寄付は、各都道府県及び全国的視野にあたる肢体不自由児の支えとなり、より良い社会の実現につながります。
寄付の詳細やお申し込み方法については、公式サイトをご確認ください。温かいご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
江戸川区
岩井整形外科病院

(画像引用:岩井整形外科病院)
『岩井整形外科病院』は、東京都江戸川区南小岩に位置する医療法人 岩井医療財団が運営する医療機関です。
1990年1月の開院以来、整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科、放射線科、内科、消化器内科、循環器内科、麻酔科など、多岐にわたる診療科目を掲げています。特に、椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症などの脊椎疾患に対する内視鏡下手術において、累計30,000件以上の実績を持ち、国内の約15%の手術を担当しています。
同院は、患者一人ひとりに適切な診断と最適な治療を提供し、早期の社会復帰をサポートすることを目指しています。最新の医療技術を積極的に導入し、患者の負担を最小限に抑える治療を追求しています。入院期間も短く、MED/MEL手術では4〜6日、FED/FEL手術では3〜4日と、早期の退院が可能です。
また、祝祭日を除く月曜日から土曜日まで外来診療を行い、他の医療機関に所属する医師からも選ばれる病院として信頼を得ています。
『岩井医療財団』では、医療の質向上と学問の発展を目的として、広く寄付を受け入れており、皆様からのご寄付は、各種研究活動や医療サービスの向上に大切に活用されています。
財団の公式サイトでは、研究の取り組みや学会発表の状況についても公開されており、寄付の申し込みもオンラインで受け付けています。ご寄付いただいた方には、財団の活動報告としてアニュアルレポートが送付される仕組みとなっています。
岩井整形外科病院は、これからも患者の健康と生活の質の向上に貢献し、信頼される医療の提供を続けていくことが期待されています。
品川区
東京医療保健大学

『東京医療保健大学』は、医療保健分野における高度な専門職業人の育成を目指し、科学技術に基づく正確な教育・研究および臨床活動を展開しています。同大学は、医療保健学部、東が丘看護学部、立川看護学部、千葉看護学部、和歌山看護学部、助産学専攻科、和歌山助産学専攻科などを擁し、看護学、医療栄養学、医療情報学など幅広い分野で専門的な教育を提供しています。
また、大学院には医療保健学研究科や看護学研究科が設置されており、修士課程および博士課程を通じて、研究・教育・管理能力を備えた人材の育成に力を入れています。特に、社会人が在職のまま受講しやすい開講形態を採用し、実務と学びの両立を支援している点が特徴です。
さらに、東京医療保健大学では、教育研究のさらなる充実・発展のために、企業や個人からの寄附金を広く受け入れています。寄附金は、以下のような目的に活用されます。
- 大学および大学院における教育・研究の充実
- 教育・研究活動に必要な機器・器材の購入
- 研究や教育に関わる諸経費の支援
これらの資金は、未来の医療保健分野を支える人材の育成に役立てられ、社会への貢献へとつながっています。東京医療保健大学は、学際的・国際的な視点から医療保健学を探究し、臨床現場で活躍する専門職業人の育成を使命としています。そのための教育環境の整備を進めながら、引き続き社会に貢献していくことが期待されています。東京医療保健大学および大学院の教育研究の充実発展のため、格別のご支援をお願い申し上げます。詳しくは公式サイトをご確認ください。
渋谷区
医療法人社団 創友会 ヒラハタクリニック
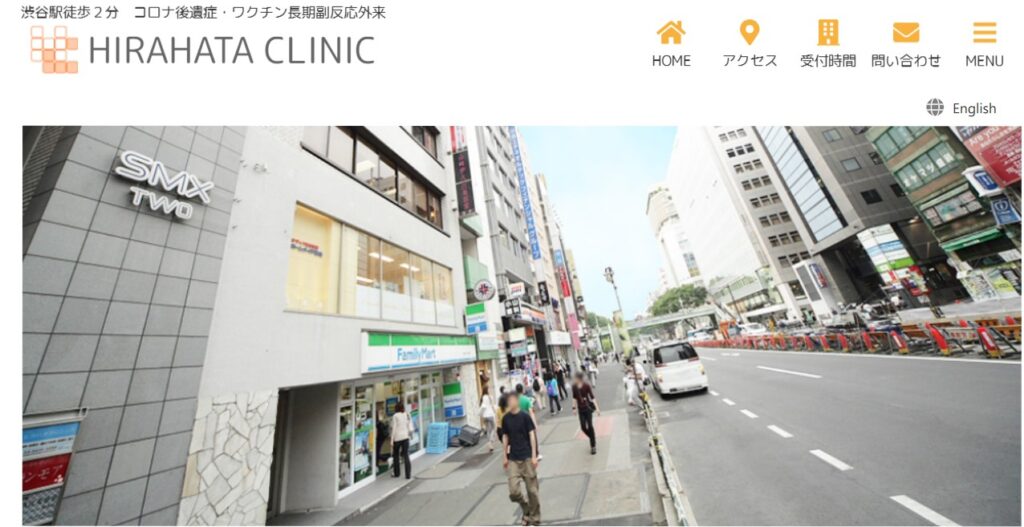
『医療法人社団 創友会 ヒラハタクリニック』は、1985年に渋谷で開設され、働く方々の健康を支えることを目的として診療を続けてきたクリニックです。受診者が求める「安心」を大切にし、迅速検査機器を導入することで早期診断・早期治療を実現しています。また、エコー、胃カメラ、大腸カメラなどの検査も時間をかけて丁寧に行い、患者一人ひとりに寄り添う医療を提供しています。
さらに、2020年からは新型コロナ後遺症の診療にも本格的に取り組み、これまでに5000人以上の患者を診察してきました。院長をはじめとする医療チームは、プログラマーやインフラエンジニアと連携し、IT技術を活用した独自のデータベースを構築しています。蓄積された膨大なデータを分析し、その結果を迅速に一般公開することで、医療従事者への情報提供や治療の向上に役立てています。また、医師向けのセミナーなどを通じて最新の知見を発信し、多くの医療機関と連携しながら治療の発展に貢献しています。
しかし、新型コロナ後遺症の診療は、通常の診療と比べて診察に時間を要するにもかかわらず、診療報酬が低く、十分な医療体制を維持することが困難な状況です。また、研究の継続や新たな治療法の開発には多くの費用がかかるため、現在の医療水準を維持し、より多くの患者に適切な医療を提供するためには、外部からの支援が必要不可欠となっています。
渋谷ヒラハタクリニックでは、いただいた寄付金を以下の目的で活用いたします。
- 診療の質向上と継続的な医療提供:医療スタッフの確保や診療体制の維持
- 研究の推進および新たな治療法の開発:新型コロナ後遺症のデータ分析・治療法の研究
- 施設・設備の維持および拡充:診療環境の整備、医療機器の更新・導入
- ITシステムの強化:後遺症データベースの管理・解析技術の向上
これからも、「渋谷で働く方々の健康を守る」という設立時の理念を貫き、患者にとって安心できる医療を提供し続けるため、皆様のご支援が必要です。温かいご協力を心よりお願い申し上げます。詳しくは公式サイトをご確認ください。
医療法人社団 MYメディカル

『医療法人社団 MYメディカル』は、日本の医療課題の解決に向け、特に予防医療に重点を置く医療機関です。関東圏を中心に健診センターを展開し、2015年に「MYメディカルクリニック渋谷」を開院。
その後、2022年には大手町や横浜みなとみらいにもクリニックを開設し、年間15万人以上の方々が健康診断や診療を受けています。
日本の医療費は年々増加し、現在では約44兆円に達しています。この負担を軽減するためには、「未病」と「早期発見・早期治療」の推進が不可欠です。MYメディカルクリニックでは、定期的な健康診断を通じて病気の早期発見を促し、医療費削減と国民の健康維持に貢献しています。
同クリニックの特徴の一つは、全ての健診センターに「アフターフォロー外来」を設置している点です。健診結果に関して不安や疑問を持つ方が、無料で医師と面談できる仕組みを提供します。これにより、再検査や早期治療のハードルを下げ、健康診断を受けた方が適切な医療につながる機会を増やしています。
また、MYメディカルクリニックは、企業向けの健康診断や予防接種にも力を入れており、これまでに4,600社以上の企業のサポートを実施。2022年度には、外来受診者数約5.5万人、健康診断受診者数約12万人、インフルエンザ予防接種の利用者数約30万人と、多くの方々に利用されています。さらに、新型コロナウイルスの予防接種においても、自治体や職域接種を合わせて80万回以上の接種を行いました。
こうした活動を全国へと広げ、より多くの方々の健康を支えていくためには、新たな健診センターの開設や、院内環境の整備、最新医療機器の導入が欠かせません。しかし、これらには多額の資金が必要であり、例えば300坪〜500坪規模の健診センターを開設する際には、内装費や医療機器の購入を含め約5億〜10億円の費用が発生します。
そのため、MYメディカルクリニックでは、社会全体で医療の質を向上させるための寄附を広く募っています。いただいた寄附金は、以下の用途に活用されます。
・クリニックの開設
・院内環境の整備
・医療機器の購入
・その他運営に必要な経費への充当
MYメディカルクリニックは、「世界で一番愛されるクリニック」を目指し、日本の医療課題の解決に向けて挑戦を続けています。その理念やビジョンに共感し、社会貢献をお考えの企業や個人の皆様からの温かいご支援が、さらなる発展の原動力となります。ご協力とご支援を心よりお願い申し上げます。詳しい情報や寄付の方法については、公式サイトをご確認ください。
杉並区
社会福祉法人 浴風会
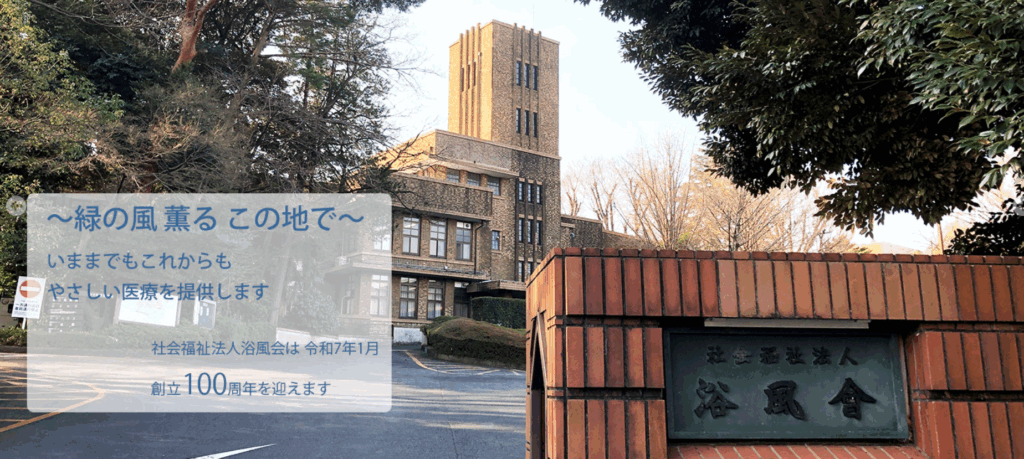
『社会福祉法人浴風会』は、1925年(大正14年)、関東大震災で被災した高齢者の支援を目的に旧内務省によって設立された施設を前身とし、以来一世紀にわたり、高齢者福祉・医療の分野で着実に歩みを進めてきました。
「高齢者が自分らしく、尊厳をもって生きられる社会の実現」を理念に掲げ、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、病院、在宅ケア支援などをはじめとする多様なサービスを、切れ目なく地域に提供し続けています。
現在では、内科・整形外科・物忘れ外来などの診療や、脳ドック・区民健診といった地域に根ざした医療を提供しつつ、認知症グループホームやデイサービス、地域包括支援センター(ケア24高井戸)などの介護福祉サービスを展開。まさに、地域医療と福祉の中核を担う存在として信頼を集めています。
2025年、浴風会は創立100周年を迎えます。これを節目に、次の100年を見据えた「創立100周年記念事業」がスタートしました。その一環として、地域福祉の未来を共に築くため、広くご支援・ご寄付を呼びかけています。
皆さまからのご寄付は、以下のような取り組みに活用されます:
- 地域に開かれた憩いと交流の場づくり
老朽化が進んだ中庭の景観整備を行い、池やベンチの改修、芝の張り替えを実施。保育園児が安全に遊べる空間を整えるなど、地域の皆さまにとって心地よく過ごせる場を創出します。 - 災害に強い地域づくり
災害時福祉救援所として指定されている施設の機能強化に向けて、簡易トイレや避難テント、炊き出し用備品などを整備し、地域と連携した防災体制を整えます。 - 脱炭素社会への貢献と緑の保全
樹木の剪定・除去など安全対策を講じつつ、杉並区の保護樹木にも指定されている構内の長寿木の保全を通じて、持続可能な環境づくりを推進します。 - 歴史的建物の保全
設立当初から残る本館と礼拝堂の補修を行い、地域の貴重な文化遺産として次世代に受け継ぎます。 - 啓発活動・人材育成
医療・福祉に関する講演会やシンポジウムの開催、福祉人材の育成支援を通じて、社会全体の支え合いの意識を高めていきます。
浴風会は、1世紀にわたる豊かな歴史と地域との深い絆を基盤に、これからも医療と福祉の中核施設としての役割を担っていくことが期待されています。また、次の100年も地域住民の憩いの場であり続けるため、施設の環境整備を進め、より安全で快適な空間づくりに取り組む計画です。快適で安心できる空間づくり、そして災害にも強く、未来に開かれた拠点としての進化を支えるこのプロジェクトには、多くの人々の協力が欠かせません。ご支援を心よりお願い申し上げます。
寄付の詳細やお申し込みは、浴風会公式サイトをご覧ください。
新宿区
国立国際医療研究センター病院

2025年4月、国立国際医療研究センター(NCGM)と国立感染症研究所(NIID)が統合し、新たに発足したのが「国立健康危機管理研究機構(JIHS)」となります。長年にわたり培われた感染症医療と研究の知見が結集されたこの機構は、日本の健康危機管理を担う中核的な存在として、国内外から高い注目を集めています。
JIHSの病院部門は、厚生労働省により「特定機能病院」に指定されており、高度で専門的な医療を提供するだけでなく、教育・研究機能を備えた医療のハブとしての役割も担っています。「高度な医療技術を、やさしさとともに」を理念に掲げ、患者中心の医療の提供と、災害や感染症の発生時に迅速に対応できる体制の整備が進められています。
同機構の使命は、「感染症に不安を抱くことのない社会の実現」にあります。日常的な医療から危機対応、さらには将来のパンデミックへの備えまで、幅広い取り組みを一体的に行っている点が特徴です。また、研究・開発や人材育成、国際的な連携なども積極的に進めており、国内のみならず世界の公衆衛生向上にも貢献しています。
これらの活動を安定的かつ持続的に推進するため、JIHSでは広く寄附を募っています。
集まった寄附金は、以下のような目的で活用されています。
- 医療の提供(病院の設備・医療機器の整備)
- 医療に関する調査・研究・技術の開発
- 医療に係る国際協力(調査・研究・技術者の研修)
- 上記成果の普及および政策提言
- 看護に関する研究・研修および人材育成
なお、寄附の際には使途を指定することも可能で、寄附者の意思を尊重した運用がなされている点も安心です。日本の医療の未来と、健康危機に強い社会の実現に向けた取り組みを支えるJIHSへのご協力と、ご支援を心よりお願い申し上げます。詳しくは公式サイトをご確認ください。
慶應義塾大学 医学部・医学研究科

『慶應義塾大学医学部・医学研究科』は、1917年の創設以来、日本の医学・医療を牽引し続けてきた教育・研究の中心的存在です。初代学部長には世界的な細菌学者・北里柴三郎博士を迎え、当初から「基礎と臨床の連携」を重視し、実学としての医学の実践を追求してきました。その理念は100年を超えた今も受け継がれ、時代に即した医療人の育成に力を注いでいます。
同学部・研究科では、知識や技術の修得に加え、思考力や倫理観、人間性を備えた「人間を診る」医師の育成を重視しています。医療の進歩に寄与する研究活動と、実社会に貢献する教育を融合させることで、次世代のリーダーとなる医師や医学研究者を多く輩出しています。
併設の『慶應義塾大学病院』は、1920年の開院以来、教育・研究・診療が一体となった大学病院として高く評価されています。患者一人ひとりに寄り添う丁寧な医療、先進的な診療技術、多職種連携による包括的ケアが特長であり、国内外から多くの患者が訪れる信頼の医療機関です。2022年には、機能性と快適性を兼ね備えた新病院棟がグランドオープンし、さらに高度な医療の提供が可能となりました。
これらの発展を支えているのが、多くの方々から寄せられる寄付です。慶應義塾では、次の100年に向けて教育・研究・医療の質を高め、未来を担う医療人材を育成するため、皆さまのご支援を広く呼びかけています。寄付金は以下のような目的で大切に活用されています。
寄付金の主な使途
- 病院の機能充実および機能改善
- 教育・研究・医療のためのキャンパス整備
- 次世代の医療人材育成の支援
- 先進医療・医学研究の推進基盤の構築
医学・医療の未来を切り拓く慶應義塾大学の取り組みに、ぜひ多くの方が関心を寄せ、支援の輪が広がっていくことが期待されます。慶應義塾大学医学部は、これからも時代のニーズに応え続けるとともに、真に信頼される医療の実現に向けて歩みを進めていくため、温かいご協力・ご支援を心よりお願い申し上げます。詳しくは公式サイトをご確認ください。
公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン

『公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン』は、病気と闘う子どもとその家族のために“第二のわが家”を提供する滞在施設です。自宅から遠く離れた高度小児医療を受けるための病院に子どもが入院・通院する場合、家族は生活拠点を離れて長期間滞在せざるを得ません。こうした家族の精神的・経済的な負担を少しでも軽くし、子どもと家族が一緒に安心して過ごせる環境を整えることがハウスの使命です。
全国には2024年12月現在で12カ所の「ドナルド・マクドナルド・ハウス」が設置され、利用者は1人1日1,000円という低廉な料金で宿泊することができます。施設内には自炊のできるキッチンやリビング、洗濯設備などがあり、ご家族が自宅のようにくつろぎ生活できる環境が整っています。家族同士の交流も生まれ、孤立しがちな闘病生活にあたたかなつながりをもたらしています。
日本では難病に苦しむ子どもが約14万人、その家族も含めると困難を抱える人々はさらに多くなります。入院中の子どもを見守るため、家族は二重生活による経済負担や精神的なストレスにさらされます。ハウスは、こうした家族に安心の居場所を提供し、生活面でも心の面でも大きな支えとなっています。
この活動を支えるのが、企業や個人からの寄付、各地での募金活動、そして多くのボランティアの皆さんの存在です。公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパンは、「患児と家族の支援」「ボランティア文化の醸成」「医療を社会で支える仕組み作り」の3つを柱とし、寄付金は以下のような目的で大切に活用されています。
寄付金の主な使途
・ドナルド・マクドナルド・ハウスの建設や運営
・既存ハウスやファミリールームの運営(日常的な備品購入・光熱費等の維持管理)
・家族支援プログラム
寄付は一時的なものだけでなく、継続したご支援、物品の寄贈、現地でのボランティア参加など、多様な形で募られています。その一つひとつが、病気の子どもとその家族が安心して治療に向き合い、希望を持って過ごせる社会づくりにつながっています。寄付の詳細やお申し込み方法については、公式サイトをご覧ください。
台東区
公益財団法人ライフ・エクステンション研究所付属永寿総合病院

『公益財団法人ライフ・エクステンション研究所付属永寿総合病院』は、東京都台東区に位置する地域医療の中核的な存在として、多くの住民から信頼を寄せられています。
「人々がいつまでも健康にこの町で暮らせる街づくり」を理念に掲げ、急性期医療を中心とした幅広い診療分野を提供しています。産科や小児科から認知症ケア、緩和ケアに至るまで、患者が安心して治療を受けられるよう、質の高い医療と快適な環境を整備しています。
また、地域住民の声に真摯に耳を傾け、安心・安全で納得できる医療サービスを実現するため、職員全員が日々尽力しています。医療の質をさらに向上させるべく、設備やサービスの充実にも注力しており、その取り組みを支える重要な資金として、寄付が活用されています。
寄付金は、以下のような用途に用いられています:
- 病院に必要な設備の拡充
診療エリアや病室の改修、待合室の快適性向上、最新医療施設の整備など、患者が快適に過ごせる環境の整備に使用されています。 - 病院に必要な機器・消耗品の購入
最新の診断機器や治療機器の導入を進めるとともに、診療に欠かせない消耗品を確保し、安全で効果的な医療の提供を実現しています。 - 成人病を中心とした予防治療等の調査・研究
高血圧、糖尿病、心疾患などの成人病(生活習慣病)に関する研究を推進し、新たな予防法や治療法の開発を目指しています。これらの活動は、地域全体の健康向上に大きく貢献しています。
永寿総合病院では、寄付金の運用において透明性を重視しており、支援者へは活動報告を通じて、その成果が伝えられています。寄付を通じて、地域医療の未来を支えることができるだけでなく、多くの命を救う手助けにもなります。
より良い医療環境の実現と、健康で安心して暮らせる社会の構築のために、皆さまの温かいご支援をぜひお願いいたします。詳しい情報や寄付の方法については、公式サイトをご確認ください。
社会福祉法人 浅草寺病院
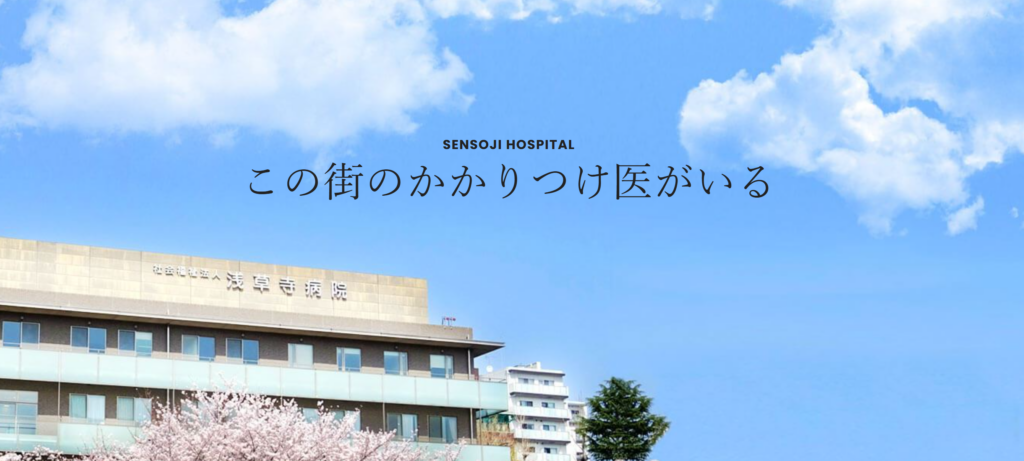
『社会福祉法人 浅草寺病院』は、東京都台東区浅草に位置する、急性期から慢性期までの包括的な医療を提供できるケアミックス病院です。地域社会に愛され、かかりつけ医として頼られる医療機関を目指し、その役割を果たし続けています。「思いやりの精神のもとにあたたかい医療を提供する」ことを理念として掲げ、患者様一人ひとりのニーズに応じた丁寧なケアを実現するために、病院全体で質の向上に取り組んでいます。
昨今では、物価高騰により相次ぐ光熱水費や食料品、医療材料等の値上げや人件費の高騰、2024年問題(医師の働き方、時間外労働の制限)による医療人材不足が顕著となっている中で、浅草寺病院では、安心して医療を受けられる環境を整備し、医療の質を向上させるために、寄付金を募集しています。皆さまからいただいたご寄付は、以下の目的に活用されています。
- 安心・安全な医療を提供するために必要な設備・機器の拡充
診療室や病室の改修、最新医療機器の導入など、医療環境の整備を進めています。これにより、患者様が安心して治療を受けられるとともに、質の高い医療を提供できる体制を構築しています。 - アメニティ向上のために必要な備品の購入
患者様が快適に過ごせるよう、必要な備品を整備しています。リラックスできる空間づくりを目指し、入院や診療中の負担を軽減する環境を整えています。 - 職員への給与の支払い
優秀な医療スタッフの確保と、働きやすい職場環境の維持に努めています。職員への給与は、質の高い医療サービスの提供を支える重要な要素であり、患者様に最適なケアを届けるための基盤となっています。
浅草寺病院は、寄付金の運用において透明性を重視しており、支援者の皆さまにはその使途を明確にお知らせしています。ご寄付はすべて、地域医療の発展と患者様のための環境整備に大切に活用されています。
寄付についての詳細やお申し込み方法は、公式サイトをご覧ください。皆さまの温かいご支援を心よりお待ちしております。
中央区
聖路加国際病院

『聖路加国際病院』は、1901年の開院以来、高度な医療技術と温かみのあるケアを提供し続けている医療機関です。1920年には聖路加国際大学が開学し、創設者トイスラー博士が掲げた「キリスト教の偉大な愛の力をだれもがすぐわかるように」という理念のもと、120年以上にわたり医療と教育の発展に貢献してきました。
また、2014年には聖路加国際大学と聖路加国際病院が法人として統合され、それぞれの特長を活かしながら相乗効果を発揮する体制が整えられました。これに伴い、中期ビジョンとして「The Art of Quality」を掲げ、2025年の達成を目指して、患者やその家族、医療従事者、学生にとって質の高いサービスを提供することを目標としています。
聖路加国際大学では、医療・看護の発展を支え、社会に貢献できる人材を育成するために、寄付金をさまざまな目的で活用しています。主な使途は以下のとおりです。
- 教育研究維持充実資金:医療・看護の教育や研究を支援し、大学や病院の施設・環境整備に活用されます。
- 公衆衛生大学院 教育振興基金:公衆衛生学研究科における奨学金や教育研究の充実に役立てられます。
- 聖ルカ保健師奨学基金:地域や学校、企業などで健康を推進する保健師を目指す学生への給付奨学金として活用されます。
- 未来の助産師奨学基金:24時間体制の分娩実習を含む、助産師養成のための給付奨学金に充てられます。
- 大学史編纂・自校教育資料保存展示事業資金:聖路加国際大学の歴史や理念を学生や社会に広く伝えるための活動を支援します。
- るかなび基金:地域住民が自らの健康を守るための健康支援サービスの提供などに活用されます。
聖路加国際病院と聖路加国際大学は、今後も質の高い医療と教育を提供し、社会に貢献していくことを目指しています。寄付の詳細や申し込み方法については、公式サイトをご確認ください。
国立がん研究センター

がんは日本人の2人に1人が罹患し、3人に1人が命を落とす病気と言われています。そのような現実に向き合い、治療や予防、研究の最前線を担っているのが『国立がん研究センター』です。1962年の設立以来、日本におけるがん対策の中核機関として、医療・研究・人材育成・情報発信といった多面的な取り組みを行ってきました。
現在、同センターは中央病院や東病院などの高度医療機関をはじめ、先端医療開発センター、がんゲノム情報管理センターなど複数の専門機関で構成され、臨床と研究を融合した体制を整えています。また、全国のがん診療連携拠点病院とのネットワークを通じて、地域格差のない医療の実現にも取り組んでいます。
センターの大きな特徴のひとつは、研究成果を迅速に医療現場へと反映させる「トランスレーショナルリサーチ」の推進です。がんのメカニズム解明からゲノム医療、免疫療法の開発に至るまで、国内外の研究者と連携しながら、未来の医療を切り拓いています。
このような最先端の取り組みを支えているのが、公的資金に加えて、広く一般の方々からの寄付です。
国立がん研究センターでは、皆さまからの寄付金を以下のような事業に活用しています。
- ゲノム解析・免疫療法など革新的ながん研究
- 新薬開発や治験の体制強化
- AI・ビッグデータによる診断支援システムの整備
- 小児・希少がんなど支援が届きにくい領域への支援
- 病室の改修やアメニティ整備など療養環境の充実
- 信頼性の高いがん情報の発信と情報基盤の整備
「がんになっても安心して暮らせる社会」を目指して、国立がん研究センターはこれからも進化を続け、がんとともに生きるすべての人を支えるために、寄付というかたちで未来の医療を応援していただけますと幸いです。ぜひ、温かいご支援をお願い申し上げます。詳細は公式サイトをご覧ください。
中野区
南東北グループ医療法人財団 健貢会 総合東京病院

『医療法人財団 健貢会 総合東京病院』は、「すべては患者さんのために」という理念のもと、医療機器・設備の充実、診療体制の強化、人材の確保・育成、地域医療との連携に力を入れてきた総合病院です。高度な医療技術と質の高い医療サービスを提供し、地域の中核的医療機関として重要な役割を担っています。
2022年には、東京都より中野区初の地域医療支援病院として承認され、地域医療の充実に貢献しています。特に、地域の医療機関との連携を強化するため、逆紹介の推進や地域医療従事者への研修会を通じた最新医療情報の提供を行っています。また、救急医療においては、24時間365日体制を整え、横断的な診療科のバックアップ体制を確立するとともに、救急救命士の積極的な登用を進めています。その結果、2023年度の救急受け入れ台数は6,500台を超えるなど、地域の救急医療の要として機能しています。
今後も、診療体制の強化、院内設備の整備、地域との連携を一層深めることで、地域住民の健康を支える医療機関としての役割を果たしていく方針です。
総合東京病院では、より高度な医療の提供と医療水準の向上のため、皆さまからのご寄付を活用させていただいております。寄付金は以下のような目的で使用され、患者さんに最適な医療環境を提供するために役立てられています。いただいた寄付金は、以下のような目的に活用されています。
- 医学研究教育の充実
最先端の医学研究を推進し、より効果的な治療法の開発や医療技術の向上を目指します。 - 最新医療機器の購入
高度な診断・治療を可能にする最新の医療機器を導入し、患者さんへの負担を軽減しながら、より精度の高い医療を提供します。 - 医療スタッフの育成
医師・看護師・医療技術者の教育・研修を充実させ、高度な医療技術と患者中心のケアを提供できる専門家を育成します。
総合東京病院では、寄付金の透明性を確保し、支援者の皆さまへ定期的な活動報告を行っています。皆さまのご支援が、未来の医療の発展と地域医療の充実に大きく貢献します。寄付の詳細や申し込み方法については、公式サイトをご覧ください。
練馬区
公益財団法人東京都医療保健協会 練馬総合病院

『公益財団法人東京都医療保健協会 練馬総合病院』は、地域医療の充実を目指し、患者や地域住民に安心と信頼の医療を提供する中核的な医療機関です。同院の経営理念は、「職員が働きたい、働いてよかった、患者がかかりたい、かかってよかった、地域があってほしい、あるので安心、といえる医療の実現」にあります。
単なる診療の場としてではなく、“健康に関するお世話”を軸とし、職員・患者・地域住民・地域医療機関・行政が一体となる「新しいモデル」としての病院を目指しています。また、健康に関する情報発信の拠点としての役割も担い、地域の方々が気軽に相談できる環境づくりにも力を入れています。
練馬総合病院では、急性期医療を中心に、幅広い診療科を備え、高度な医療技術と温かみのあるケアの両立を大切にしています。さらに、救急医療にも積極的に取り組んでおり、地域の救急搬送体制の一翼を担ったり、医療スタッフの育成にも注力し、次世代の医療を担う人材の育成を通じて、地域医療のさらなる発展に貢献しています。
このような活動を支えるため、同院では寄付の受け入れを行っています。国民の保健向上に必要な医療の研究・実践を進め、地域医療の充実を図ることを目的とし、寄付金は病院の運営や診療体制の強化、設備の充実などに活用されます。地域に根ざした質の高い医療を提供し続けるためにも、多くの方々の理解と支援が求められています。
寄付の詳細やお申し込み方法の詳細については、公式サイトをご覧ください。
文京区
一般社団法人 日本小児血液・がん学会

『日本小児血液・がん学会(JSPHO)』は、小児の血液疾患やがんの診療・研究・教育の発展を目的とし、全国の医師や研究者が協力し合いながら活動する専門学術団体です。小児がんや血液疾患は、発症頻度こそ成人に比べ低いものの、患者やご家族にとって大変深刻な課題であり、最先端の医療体制や優れた専門医の育成が欠かせません。JSPHOでは、子どもたちがより良い医療を受けられる未来を目指し、診療の質向上と研究の推進、専門医の育成、正確な医療情報の普及に力を入れています。
この学会は、会員である医師や研究者同士のネットワークを通じて、小児血液腫瘍に関する最新情報の共有、治療成績の向上、診断や治療ガイドラインの策定に携わっています。また、患児や家族に寄り添った支援活動や、一般の方々への啓発にも積極的に取り組んでいます。
JSPHOの活動を支える寄付金は、以下のような大切な目的に活用されています。
- 学会として行う小児血液・がんに関する研究活動や調査への支援
- 国内外の医療者・研究者を対象とした教育・研修・学術集会の開催
- 若手医師・研究者の育成や優秀な人材の発掘・支援
- 診療ガイドラインや患者向け情報資料の作成・普及
- 小児がん患者やその家族への相談支援活動
- 小児がんや血液疾患に関する社会啓発および正しい知識の普及
ご支援いただいた資金は、未来を担う子どもたちの健康と命を守るための現場で、着実に活用されます。例えば、若手医師への研究助成や海外学術交流、診療に直結する臨床研究の推進、会員向けおよび一般社会向けの講演やセミナー開催、患者や家族に向けた情報発信やサポート体制の拡充など、学会の幅広い公益活動に役立てられます。
日本小児血液・がん学会は、次世代の子どもたちが病気と向き合いながらも大きな希望を持ち、一人でも多くの命が救われる社会の実現を目指し努力を続けています。そのためには、皆さまからのご寄付による継続的なご支援が必要不可欠です。子どもたちの明日をともにつくるため、温かいご協力を心よりお願い申し上げます。
寄付の詳細やお申し込み方法については、公式サイトをご覧ください。
一般社団法人 医療安全全国共同行動

『医療安全全国共同行動(いのちをまもるパートナーズ)』は、医師や看護師をはじめ、薬剤師、臨床検査技師、歯科衛生士など多職種の医療従事者が職種の壁を越えて協働し、さらに患者・市民とのパートナーシップのもと、誰もが安心して受けられる安全な医療の実現を目指して活動を続けてきた全国組織です。
2008年の発足から、法人化した現在も、共同行動は二つの大きな使命を担いながら進化を続けています。一つは、全国の医療機関における医療安全の具体的な「行動目標」を支援すること。転倒・転落の防止や急変時対応の強化、事例分析からの改善支援など、実践的な対策に取り組む医療機関を支えています。また、教育動画の配信や研修、レポートの発行、実践ハンドブックの刊行など、医療の現場に役立つ知識とツールを広く提供しています。
もう一つの使命は、患者・市民とともに安全な医療をつくるための啓発活動です。高齢化や地域医療の進展に伴い、今後は地域包括ケアにおける医療安全の確保も大きな課題となっています。共同行動では、こうした社会の変化に応じ、より身近な医療の安全性を高めていくための取り組みにも力を入れています。
これらの活動をさらに発展させていくため、現在、広く寄付金を募っており、以下の用途に活用されます。
- 医療安全研修会・セミナー、教材・ツールの開発と普及
- 医療従事者や管理者向けの教育活動、eラーニングの拡充
- 医療事故や有害事象の調査・分析・情報発信事業
- 一般市民・患者向けの啓発活動
- 医療安全文化の醸成や行動目標の「見える化」推進
同団体への支援は、日本全国の医療機関における安全対策の強化につながり、結果として患者・市民の生命と健康を守る重要な役割を果たします。皆さまのご支援が、全国の医療現場で安全で質の高い医療を実現し、患者・市民の命と健康を守る力となります。
寄付の詳細やお申し込み方法については、公式サイトをご覧ください。
港区
東京慈恵会医科大学附属病院

学校法人 慈恵大学は、東京慈恵会医科大学のほか、慈恵第三看護専門学校および慈恵柏看護専門学校の2つの看護専門学校を運営し、質の高い看護教育の提供に力を注いでいます。
附属病院である『東京慈恵会医科大学附属病院(慈恵医大病院)』は、長い歴史と高度な医療技術を誇る総合病院で、「病気を診ずして病人を診よ」という理念のもと、高度な医療技術と温かみのある医療を提供しています。患者を一人の人間として尊重し、心と体の両面に寄り添う「慈恵の心」に基づいた、患者中心の医療を実践し続けていることが特徴です。
また、東京慈恵会医科大学などの教育の場では、そんな「慈恵の精神」に則り、単に医療技術を学ぶだけでなく、人間性を育む教育にも重点を置き、有能な医師や看護師の育成に取り組んでいます。特に看護教育では、臨床現場での実践的な学びを通じ、患者に寄り添う看護を提供できる人材を輩出しています。
同法人では、未来の医療と教育の充実を図るため、寄付金を募集しています。寄付金は、以下のような用途に活用されます。
- 老朽化した第三病院の建て替え
狛江市・調布市と協議を重ねながら、地域の医療ニーズに応える新病院の建設を計画しています。 - 国領校舎の建て替え・医療施設の充実
より充実した医療施設の整備を通じて、高度な医療の提供を目指しています。 - 最新医療機器の導入
- 医学研究の推進
- 医師・看護師の育成支援
こうした取り組みを実現するためには、多額の資金が必要となります。慈恵大学では自助努力による財政運営を続けていますが、医療機関や大学を取り巻く環境の変化により、資金調達には限界があるのが現状です。
皆様の温かいご支援は、未来の医療の発展に寄与し、多くの人々の健康を支える大きな力となります。
詳しい情報や寄付の方法については、公式サイトをご確認ください。
東京大学医科学研究所附属病院

『東京大学医科学研究所附属病院』は、最先端の医学研究と高度な臨床医療を融合させた特定機能病院です。東京都港区白金台に位置しており、「あたたかい全人的医療を実践する」「倫理性・科学性・安全性に基づいた、新治療法を開発する」「透明性を保ちつつ、患者の権利を最大限に尊重する」といった3つの理念に基づき、高度な医療技術と温かい患者ケアを提供しています。
東京大学医科学研究所附属病院の特徴的な取り組みとして、プロジェクト診療があります。これは、比較的患者数の少ない病気や難治性の疾患について、プロジェクト化して診療や研究を行うものです。また、基礎研究の成果を臨床に応用するトランスレーショナルリサーチにも力を入れており、東京大学医学部附属病院と共に「東京大学拠点」となっています。
看護部門では、プライマリーナーシングとペア・システムを導入し、患者さんとの関係構築を図りつつ、看護師一人ひとりの責任感とやりがいを育んでいます。また、e-learningシステムの導入や認定看護師資格取得のサポートなど、看護師のスキルアップとキャリア形成を支援しています。
地域貢献の一環として、市民公開医療懇談会を定期的に開催し、様々な医療テーマについて講演を行っています。これにより、地域住民の医療リテラシー向上に貢献しています。
東京大学医科学研究所附属病院では、より質の高い医療を提供するために「医科研病院募金」を通じて寄付を募っています。この募金は主に以下の3つの目的のために活用されます:
- 診療の充実:放射線設備、検査機器、手術室、リハビリテーション室など、診療に関する設備・機器の整備
- 療養環境の整備:病棟や外来環境の整備を通じて、患者さんがより快適に過ごせるような療養環境づくり
- 医学の進歩:医科学研究所附属病院の特徴であるプロジェクト診療などの更なる進歩
これらの取り組みを通じて、東京大学医科学研究所附属病院は、患者中心の医療と最先端の研究開発を両立させ、日本の医療の発展に貢献し続けています。寄付の詳細や申し込み方法については、公式サイトをご確認ください。
公益財団法人痛風・尿酸財団

『公益財団法人 痛風・尿酸財団』は、痛風や高尿酸血症などの疾患に関する正しい知識の普及と、関連医療・研究の発展、患者支援を目指して活動する公益法人です。生活習慣の変化に伴い、これらの疾患は近年ますます増加傾向にあります。痛風の原因とされる「尿酸」は、今なお医学的に未解明な点も多く、基礎から臨床まで幅広い分野での研究が進められています。そうした背景の中、痛風・尿酸財団は、専門医療の向上と、国民への啓発活動の両面から、日本の健康社会に貢献し続けています。
この財団では、次のような活動を行っています。
- 痛風・尿酸代謝異常に関する最先端の基礎・臨床研究への助成
- 医師や看護師、栄養士など医療従事者向けの研修・セミナーの開催
- 全国の協力医療機関ネットワークの整備と最新医療情報の共有
- 一般市民向けの講演会やパンフレットの発行、Webサイトによる啓発活動
これらの活動によって、新たな治療法や診断技術の発見、専門医療体制の整備、正しい疾患知識の普及が推進されています。たとえば、若手研究者への研究助成は日本の医療研究の発展につながり、啓発活動は患者さんやそのご家族が早期受診・適切な治療につながるきっかけを生み出しています。
寄付金は、主に以下の用途で活用されます。
- 痛風・尿酸分野の研究助成および若手研究者の育成
- 医療従事者への研修や最新の医療知識の普及
- 市民へのわかりやすい疾患啓発活動(冊子・講演など)
- 専門医療機関ネットワークの維持・拡充
痛風や尿酸に関する研究と正しい知識の普及は、未来の医療の質を高めるだけでなく、患者さん一人ひとりの生活の質を守ることにもつながります。
日本の医療と健康の未来を支えるために、多くの方々からの継続的な支援が、これからも求められています。寄付の詳細については、痛風・尿酸財団の『公式サイト』にてご確認いただけます。
昭島市
NPO法人 東京こどもホスピスプロジェクト

『東京こどもホスピスプロジェクト』は、生命を脅かす病気を持つ子どもたちとその家族のために、小児緩和ケアの提供と「こどもらしい毎日」を支える活動を続けている団体です。病気や入院によって、子どもたちはさまざまな制約や孤独、成長や夢への不安を抱えることがあります。東京こどもホスピスでは、医療とともに教育・音楽・芸術など多様な体験を取り入れ、子ども一人ひとりの“今”を大切にし、ご家族も含めた心の支えとなる場を作っています。
このホスピスが目指すのは、単なる医療的ケアにとどまらず、子どもたちが遊びや学び、友達と過ごす時間など、成長に欠かせない経験を積める場所を提供することです。また、ご家族が悩みや不安を分かち合い、安心して日々を送れるよう、きめ細やかなサポート体制も整えています。
東京こどもホスピスの活動は、多くの方々のご寄付により支えられ、寄付金は下記のような用途に活用されています。
- 病気や障がいのある子どもと家族が安心して過ごせる施設の運営
- 子どもたちへの教育・芸術・音楽など多様な体験活動の実施
- 看護師・医師・ボランティアなど支援スタッフの育成や研修
- ご家族向けの相談・交流プログラムや、心のケア活動
- 小児緩和ケアへの理解を広めるための啓発事業・広報活動
これらの活動により、厳しい状況にある子どもとその家族が、社会とつながりながら希望をもって毎日を過ごせるよう、幅広いサポートが行われています。夢や日常をあきらめずに過ごせる場所を未来へつなぐために、命の輝きを支えるパートナーとしてぜひ皆さまのご協力が大きな力となります。
寄付の詳細やお申し込み方法については、公式サイトをご覧ください。
清瀬市
学校法人 明治薬科大学

『明治薬科大学』は、1902年に恩田重信によって創設された、長い歴史と確かな実績を持つ薬科大学です。「薬学の普及」「有為な薬剤師の養成」「医薬分業の実施」という建学の精神のもと、「薬学を通じて国民の保健衛生に貢献する」ことを理念に掲げ、120年以上にわたり薬学教育と研究の発展に寄与してきました。
現在は、6年制の薬学科と4年制の生命創薬科学科の2学科体制で運営されており、薬学科では高度な医療人としての薬剤師を、生命創薬科学科では次世代の創薬研究者・専門技術者の育成を目指しています。両学科とも実践的で倫理的な教育を重視しており、教育内容の「見える化」や学修成果の可視化にも力を入れています。
理事長・佐川賢一氏は、急速に進む教育・研究の国際化や多様化に対応しながら、「大学の存在価値そのものが問われる時代」にあるとの認識のもと、持続可能な教育・研究体制の構築を進めています。学長・越前宏俊氏も、教育の質保証や社会との連携、学生の主体的学びの促進を重視し、「地域社会および国際社会とともに歩む大学」の実現を掲げています。
そうした取り組みを支えるため、2009年に設立された「明治薬科大学基金」では、さまざまな教育・研究活動に対する支援を目的に、皆さまからのご寄付を募っています。
寄付金は、以下のような事業に活用されています。
- 学部生および大学院生への奨学支援
- 外国人留学生への支援および受け入れ施設の整備
- 教育・研究環境および学生寮等の施設整備
- キャンパスアメニティの向上(学生生活支援、環境配慮活動など)
- 公開講座や講演会等を通じた地域・社会への貢献
- その他、基金の目的に沿った大学の教育・研究支援事業
今後も、明治薬科大学は、建学の精神を受け継ぎつつ、時代の変化に応じた柔軟で先進的な教育・研究を通じて、薬学の未来を担う人材の育成と社会貢献を続けていきます。詳しくは公式サイトをご確認ください。
三鷹市
医療法人社団 實理会 東京国際大堀病院

東京都三鷹市にある『東京国際大堀病院』は、2019年に医療法人社団實理会によって開設された、泌尿器科および婦人科のロボット支援手術に特化した高度専門病院です。開院からわずか数年で急成長を遂げ、現在では前立腺がんのロボット手術において東京都内で最多、全国でも第3位という実績を誇っています。さらに、泌尿器科・婦人科全体でのロボット手術件数では全国2位を記録しており、国内外から高い評価を受けています。
この病院が目指しているのは、「がんを克服して、人生を楽しむための医療」。がんという言葉にとらわれず、患者一人ひとりの“その先の人生”に寄り添うことを大切にしています。最先端の医療機器と高い専門性を備えた医療チームが、身体的・心理的・社会的なサポートを含めた「包括的な治療環境」を提供しています。
一方で、医療現場を取り巻く経済状況は厳しさを増しており、物価や人件費の上昇に対して診療報酬の伸びは限定的です。高額なロボット機器を中心とする同院では、機器の維持費や光熱費といった負担が非常に大きくなっており、持続的な運営には社会全体からの理解と支援が不可欠となっています。
そのため、東京国際大堀病院では、より良い医療体制の維持・発展のために、皆様からの寄付を広く受け付けています。いただいた寄付金は、以下のような目的で活用されています。
- 病室の改修など、患者にとって快適な療養環境の整備
- 院内の情報システム環境の整備と高度化
- 手術支援ロボットをはじめとする医療機器の導入・更新
- その他、医療の質を保つために必要な運営経費の補填
東京国際大堀病院は、これからも「人にやさしく、技術に強い病院」を目指して、進化し続けていきます。
その歩みを支える温かなご支援をお願い申し上げます。詳しくは公式サイトをご確認ください。
杏林大学医学部付属病院

『杏林大学医学部付属病院』は、東京都三鷹市に位置する1,055床を有する特定機能病院であり、多摩地域における高度医療の中核を担っています。地域住民の健康と福祉に貢献するため、最先端の医療技術と温かい患者ケアを両立させ、患者中心の医療を提供しています。
当院は1999年に日本初の眼科総合診療センター「杏林アイセンター」を開設し、白内障、緑内障、網膜疾患、糖尿病網膜症など多岐にわたる眼科疾患に専門的かつ総合的な診療を提供しています。さらに、高度救命救急センター、総合周産期母子医療センター、がんセンター、脳卒中センター、臓器・組織移植センター、もの忘れセンターなど多彩な専門センターを設置し、24時間体制で救急医療に対応。特に三次救急医療を担う高度救命救急センターは、重篤な患者の救命と治療において重要な役割を果たし、地域医療の最後の砦として機能しています。
教育・研究面では杏林大学の臨床医学教育と連携し、研修医や医学生の育成に注力。臨床研究や医療技術の開発も積極的に推進し、常に最先端の医療を地域に提供しています。地域医療機関との連携強化により、医療資源の効率的な活用と情報共有を進め、地域全体の医療水準向上に貢献しています。
杏林大学では、「KYORIN GAKUEN FUND」を通じて教育・研究活動の発展と患者サービスの向上を目指し、寄付を募っています。いただいた寄付金は以下のような目的に活用されます。
- 最新医療機器の導入・整備
高度医療の提供に不可欠な検査機器や治療装置の導入・更新に充てられます。 - 教育環境の充実
医学生や研修医のための教育施設の整備や教材開発に活用し、質の高い臨床教育を支えます。 - 研究活動の推進
臨床・基礎研究のための設備投資や研究費用に使われ、医療技術の革新を促進します。 - 奨学金支援
経済的に困難な学生に対する奨学金の支給を通じて、優秀な人材育成を支援します。 - 地域医療・患者支援の充実
がん相談支援センターなど患者支援施設の充実や地域医療連携の強化に役立てられます。
詳細や寄付の申し込み方法については、公式サイトをご覧ください。皆さまの温かいご支援を心よりお待ちしております。
武蔵村山市
独立行政法人国立病院機構 村山医療センター
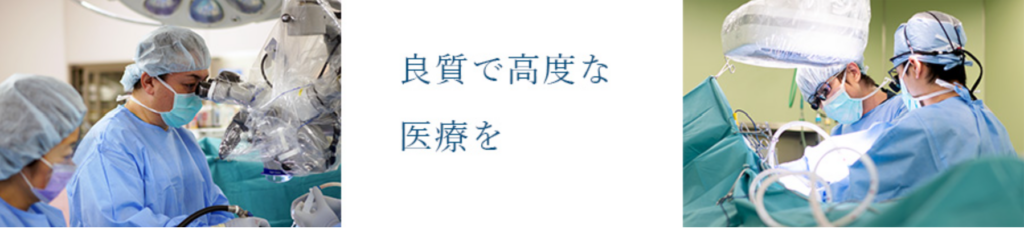
東京都武蔵村山市にある『独立行政法人国立病院機構 村山医療センター』は、昭和16年、陸軍病院として発足し、その後、国立村山療養所、国立療養所村山病院を経て、平成16年4月には、全国143施設を有する独立行政法人国立病院機構の1つとして新たにスタートしました。
脊椎・脊髄疾患や運動器疾患の診療を専門とする医療機関として、独立行政法人国立病院機構に属し、特に脊髄損傷や重度の整形外科疾患の治療・リハビリテーションにおいて、国内でも高い評価を受けています。充実した医療設備と専門医による高度な治療体制を整え、患者一人ひとりに最適な医療を提供しています。
同センターでは、脊髄損傷や運動器疾患の診療だけでなく、リハビリテーションや研究にも力を入れています。特に脊髄再生医療の研究は、慶應義塾大学などの研究機関と連携しながら進められ、運動機能回復に向けた最先端の治療法が模索されています。回復期リハビリ病棟、整形外科病棟、脊髄損傷専門病棟などを備え、個々の患者に適したリハビリプログラムを提供しているのも特徴です。充実したリハビリ体制のもと、多くの患者が機能回復を目指して治療を受けられています。
また、より良い診療環境を整備し、患者に質の高い医療を提供するため、同センターでは寄附金の受け入れを行っています。寄附金は適切に管理され、以下のような目的に活用されます。
- 医療を提供
- 医療に関する調査および研究の推進
- 医療技術者の研修
- その他、診療環境の充実に資する取り組み
今後も高度な専門医療の提供、医療技術の発展、リハビリテーションの充実とともに、より多くの患者が安心して治療を受けられる環境を整え、質の高い医療を提供し続けることを目指しています。詳細については、村山医療センターの公式サイトをご覧ください。