論文リジェクト──
そのメールを開いた瞬間、胸が締めつけられるような気持ちになったことのある人は少なくないでしょう。
「努力が否定されたようで、何も手につかない」
「査読コメントがひどすぎて、もう書きたくない」
けれども、リジェクトは研究者にとって恥ずかしいことでも、失敗でもありません。
どんな優れた研究者でも、リジェクトを何度も経験しています。むしろ、それを経てこそ論文は磨かれ、研究はより良い形へ進化します。
この記事では、
- リジェクトされたときの心の回復法
- 「ひどい」査読コメントへの向き合い方
- 査読者との関係を理解する視点
- 再投稿に向けた戦略
の4つを軸に、あなたの研究を再び前へ進めるための考え方を整理します。
論文がリジェクトされたときの心の回復法

そもそも、リジェクトの瞬間に落ち込むのは、あなたが真剣に研究に向き合ってきた証拠です。
まずは、落ち込む自分を否定しないでください。
私も研究をしていますが、一つの研究を完成させるために途方も無い時間がかかることは理解しておりますので、リジェクトの時の落ち込みは悔しいほどですよね。
ステップ1:距離を置く
通知メールを受け取った直後は、冷静な判断ができないんじゃないかなと思います。
1〜2日間は論文から離れて、頭を休めることをおすすめします。散歩や運動、趣味の時間に充ててください。
ステップ2:感情を言語化する
「悔しい」「納得いかない」とノートに書き出すだけで、少し整理されます。
研究仲間に話すのも効果的です。誰もが経験していることだからこそ、共感してもらえるはずです。
ステップ3:リジェクト=研究を否定されたわけではない
最も重要なのは、リジェクトはあなたの研究の価値を否定されたわけではないということ。
査読の結果は、「雑誌との相性」「査読者の考え方」「研究分野の視点」といった外的要因にも左右されます。
実際、ある論文がリジェクトされたあと、よりインパクトファクターの高い雑誌に再投稿してアクセプトされた例も珍しくありません。
つまり、リジェクトは“終わり”ではなく、“別の道を探すチャンス”なのです。
「ひどい」査読コメントへの向き合い方
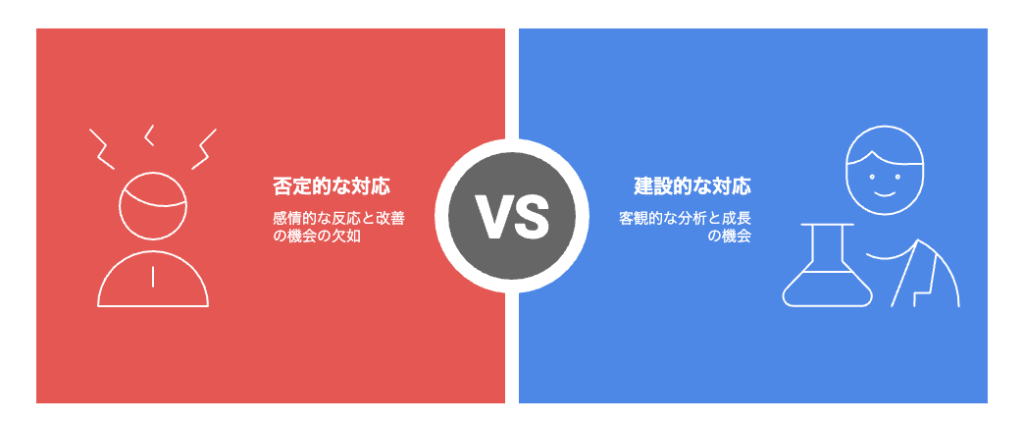
査読コメントを読むと、「人格否定のようだ」「全否定された」と感じることがあります。
しかし、そのコメントが“ひどく見える”のは、あなたが今、傷ついているからかもしれません。
査読者の多くは、あなたの研究を否定したいわけではありません。
彼らも研究の大変さを知っています。だからこそ、「できれば採択したい」「より良くしてほしい」と願いながらコメントを書いています。
ひどいコメントだと思うかもしれないが、査読者は敵ではない、仲間である
査読者は、あなたの論文を“攻撃”しているのではなく、論文をブラッシュアップする仲間です。
研究者としての経験から、「この部分を補足すればもっと伝わる」「この点を修正すれば採択される」という視点でコメントをくれています。
たとえ言葉が強く感じられても、それは文章上の表現であり、敵意があるわけではありません。
実際に会って話せば、「あなたの研究は面白い。ただ、この点をもう少し説明してほしい」と穏やかに語る人がほとんどです。
そのため、コメントを読んで否定的な感情が湧いたら、まずは数日おきましょう。
そして冷静になってから「何を指摘しているのか」を抽出します。
- 「サンプルサイズが小さい」→ 改善できる具体的な指摘
- 「研究の意義が伝わらない」→ 書き方や構成の改善で解決可能
- 「この研究は意味がない」→ 感情的コメントのため、スルーでOK
コメントを分類すると、“建設的な指摘”と“感情的な表現”が見分けられるようになります。
建設的な指摘は、むしろ歓迎すべきことです。たとえリジェクトになったとしても、次の雑誌に再投稿する際の非常に重要なコメントだからです。
レビューワーコメントへの基本スタンス
査読コメントへの回答を書くときは、
- どんなコメントにも「ご指摘ありがとうございます」から始める
- 攻撃的なコメントには「感謝+事実」で冷静に返す
- 反論が必要な場合は、文献やデータを添えて丁寧に説明する
査読は戦いではなく、共同作業です。
「誤解を解く」「改善提案に応える」という姿勢が伝わると、次の審査では印象がまったく違います。
「このレビューワーは私の研究を全くわかってくれない!」と思うかもしれませんが、それは「わかりやすく伝える工夫が足りない」だけかもしれません。
あなたほど、あなたの研究に対して理解をしている人はいません。生のデータも時間をかけて確認し、先行研究も吟味した上での研究ですから。
ですが、レビューワーは限られた情報の中で精査するしかありません。その上で建設的な議論をしようとしているだけなので、ぜひ「仲間」だと思って対応してもらえるといいかなと思います。
査読者ひどいの!?査読者との関係を理解する視点
多くの若手研究者が誤解しがちなのは、「査読者=敵」という思い込みです。しかし、査読者は論文を“落とす”ために存在しているのではありません。
査読者は、研究の難しさを身をもって知っている人たちです。
だからこそ、本音では「できれば採択したい」「良い形に直してほしい」と思っています。
彼らの目的は、あなたの研究を否定することではなく、学術的な信頼性と伝わりやすさを高めること。
そのため、時に厳しい言葉を選ぶことがありますが、それは論文をより良くするためのフィードバックなのです。
査読者との相性や考え方の違いもある
もちろん、査読者も人間です。
研究スタイルや理論への立場、分野の文化によって、意見が分かれることもあります。
つまり「リジェクトされた=研究の価値がない」ではなく、単に**“その査読者と相性が合わなかった”**という場合もあります。
たとえば、
- 臨床重視の雑誌では「統計が複雑すぎる」と言われ、
- 統計重視の雑誌では「臨床的意義が薄い」と指摘される。
このようなことは日常茶飯事です。
同じ論文を別のジャーナルに再投稿したら、あっさりアクセプトされた──そんなケースも多くあります。
リジェクトは「拒否」ではなく「方向修正」
リジェクトは「もう出すな」というサインではありません。むしろ「もう少しこうすれば通る」という、次への改善のためのサインです。
だから、落ち込む必要はありません。
査読を“批判”ではなく“提案”として捉え直すと、研究へのモチベーションが再び戻ってきます。
論文再投稿に向けた戦略
気持ちが落ち着いたら、次に進む準備をしましょう。
リジェクト後に最初にやるべきことは、査読コメントの整理です。
ステップ1:コメントを分類して整理する
Excelなどに以下のような形でまとめます。
| 査読コメント | 対応方針 | 修正箇所 | 対応状況 |
| 統計手法が不明確 | 方法の章を追記 | Methodsセクション | 完了 |
| 結果の説明不足 | 図を追加 | Figure 2 | 未対応 |
これを可視化するだけで、気持ちが整理され、「やるべきこと」が明確になります。
ステップ2:次の投稿先を戦略的に選ぶ
- テーマの適合性を最優先に考える
- インパクトファクターよりも、読者層の合致を重視
- 査読が早いジャーナルを選ぶのも有効
雑誌との“相性”が合えば、驚くほどスムーズに進むこともあります。
重要なのは、「拒否された場所で戦う」のではなく、「理解してもらえる場所を探す」ことです。
ステップ3:書き直しながら自分の成長を実感する
リジェクトは痛みを伴いますが、研究者としての成長のきっかけでもあります。
査読コメントを反映させながら書き直すうちに、自分の論理構成が整理され、研究の軸がより明確になります。
論文は「リジェクト → 改訂 → 再投稿 → 採択」というプロセスを通じて完成していくもの。
1回のリジェクトで終わりではなく、何度でも再チャレンジできるのが学術の世界です。
まとめ|リジェクトはあなたを強くするプロセス
論文リジェクトに落ち込むのは当然です。でも、冷静に考えてみれば、あなたがそこまで落ち込むのは、研究に真剣だからこそ。
- 査読者は敵ではなく、論文を磨く“仲間”
- 「ひどいコメント」に見えても、改善のヒントが隠れている
- リジェクトは研究を否定するものではなく、単なる“相性”の問題であることも多い
そして何より──
リジェクトは終わりではなく、あなたの研究をより強く、より美しく磨き上げる過程です。
少し休んだら、もう一度PCを開いてください。
あなたの研究には、まだ伝わるべき価値があります。
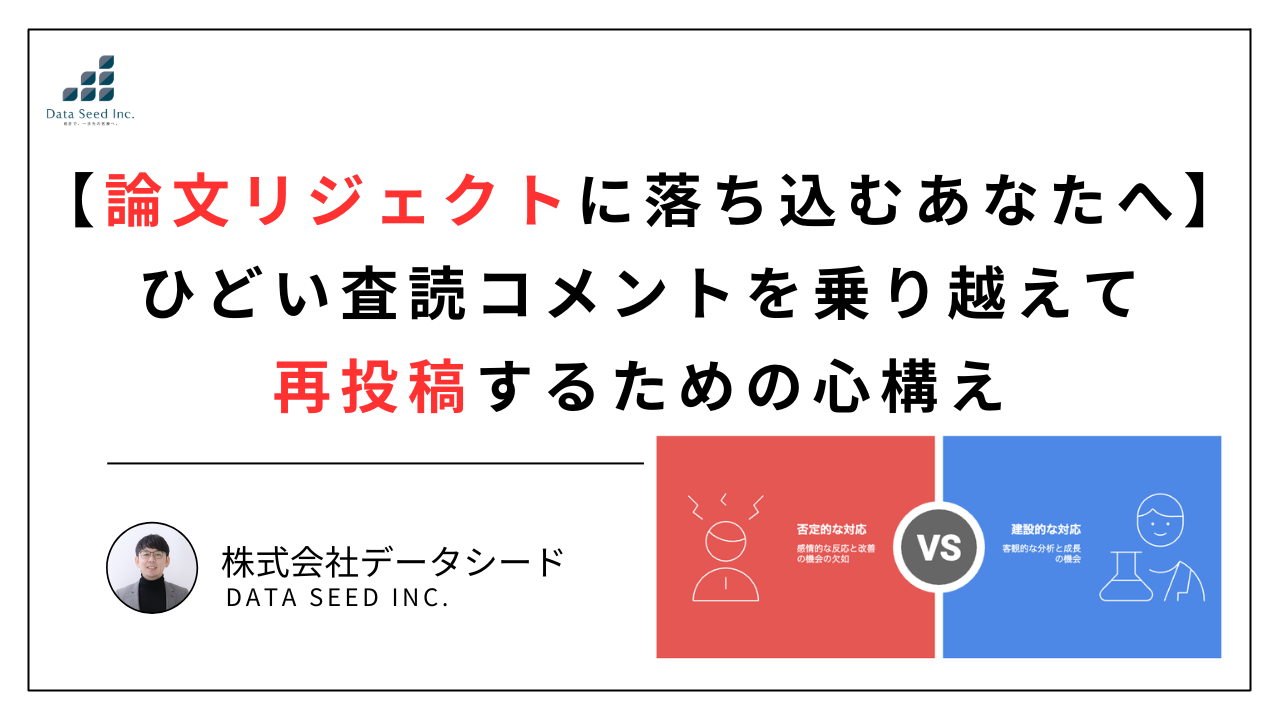
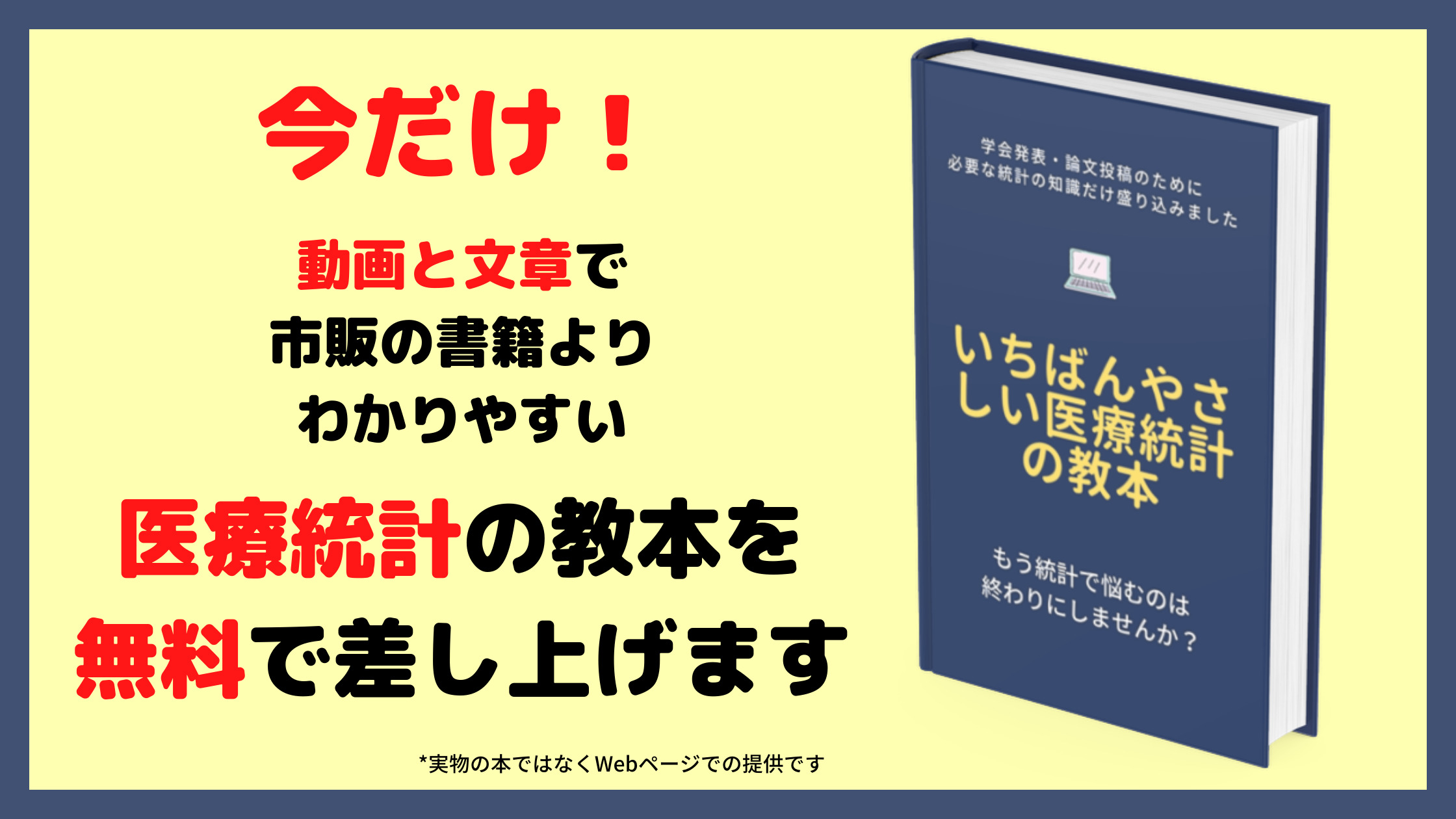
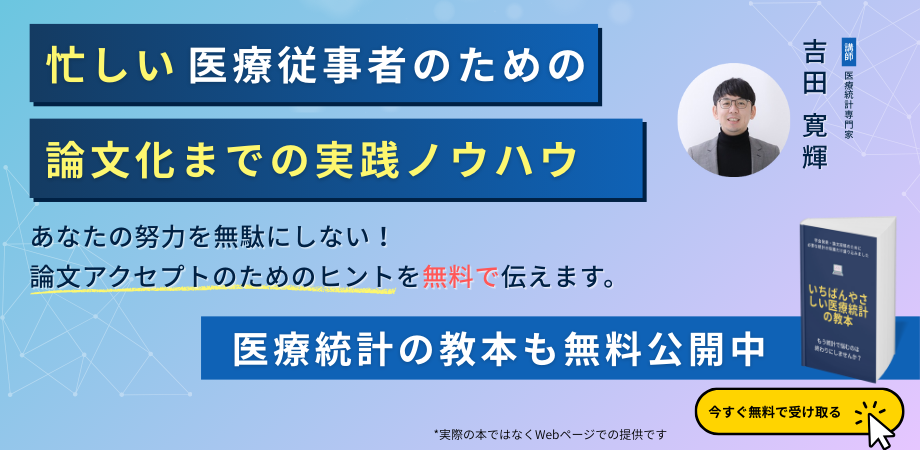
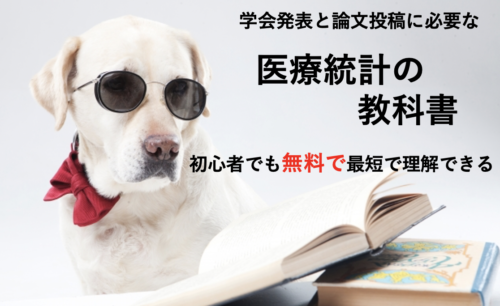

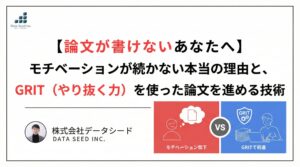
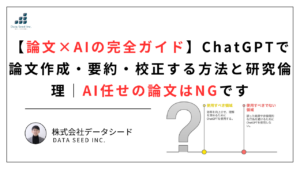

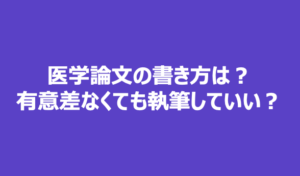
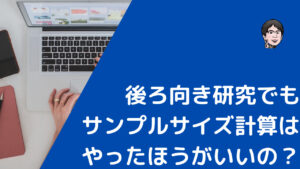
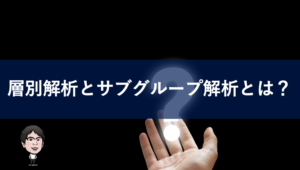

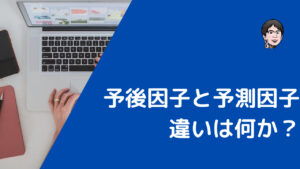

コメント